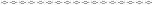<あらすじ>
父と、幼い息子と娘。水道も電気もない空き家にマットレスを敷いて三人で眠る。父は、不動産広告の看板を掲げて路上に立ち続ける「人間立て看板」で、わずかな金を稼ぐ。子供たちは試食を目当てにスーパーマーケットの食品売り場をうろつく。父には耐えきれぬ貧しい暮らしも、子供たちには、まるで郊外に遊ぶピクニックのようだ。だが、どしゃ降りの雨の夜、父はある決意をする・・。
リー・カンション、リー・イーチェン、リー・イージェ、チェン・シャンチー、
ヤン・クイメイ、ルー・インチン、 他 出演
ツァイ・ミンリャン 監督作
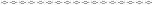
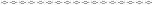
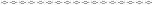
<感想>
永遠のシャオカン。
ツァイ・ミンリャン監督の商業映画引退作 『郊遊 ピクニック』
ここでもリー・カンションさんはシャオカンだった。
ツァイ・ミンリャン監督の映画の中で常に登場してくれたシャオカンは
『楽日』の時の無口な映写技師の青年ではなく
日々生きて行くのが精一杯の疲れた父親の顔だった。
雨に打たれ、強風に耐えながら広告の看板を持ち立つ仕事。
最初は遠くから、そのうち何度か目には
顔のアップになって詩のようなものを歌う彼の姿は
無防備に辛さがあふれ今にもパンクし押しつぶされそう。
シャオカンにはふたりの子供がいる。
お兄ちゃんと妹はそんなに悲観的には観えない。
というより、試食コーナーでやりすごしたり
極貧なのだけれど三人一緒だからなのかもしれない。
清潔なお風呂場でシャワーを浴び歯を磨こうと
公衆便所で歯を磨き足を洗い体を拭こうと ひとりでするのとは違う。
三人でお弁当を食べ妹はキャベツを買って一緒に寝る。
寝床のキャベツに行き場のないものがこみあげ
キャベツを絞殺し丸かじりしてしまうシャオカン。
そのキャベツを買ったお店で働くスーパーの女は
妹の髪を洗ってくれている。
廃墟で暮らす野良ワンコたちにご飯をあげにいく女がいる。
ワンコたちにはそれぞれ名前がつけてあり
「王力宏」とも呼んでいて、もしかして
『ラスト、コーション』のワン・リーホンさんのこと?と
思ってちょっとクスって和んでしまった。
隠しておいた小舟。豪雨。ひとりでむさぼるチキン。
大きな屋敷の廃墟のような壁には意味ありげな壁画。
そこをいつも哀しげな眼で眺め涙を流す女。 忘れられた蛙。
長い呼吸の末に すべてを投げ出し拒絶されたシャオカン。
まるで死後の世界のような、孤独な場面。
あるいは過ぎた日々のことなのだろうか。
今のことのようで、今のことでないような空虚。
いや、もしかしたらそういうことなのか。
あ、いや、そういうことでもあるのかとか、 ぼんやりと受け止めながら
その頼りない寂しげな背中を見つめている映画のコチラ側。
シャオカンの生きた日々。映画の住人の歳月。色んなシャオカン。
それは消えない。映画を好きでいる気持ちがあるかぎり。




*2014年12月の或る日、シネマ ジャック&ベティにて鑑賞